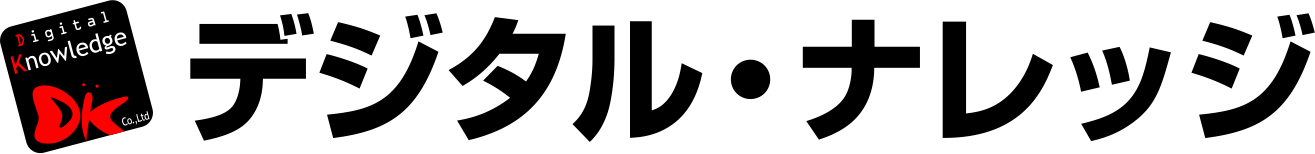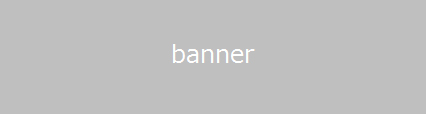いけばなを始めてみよう!基本と始め方、初心者におすすめの道具を紹介

いけばなに興味はあるけど「どうやって始めたらいい?必要なものはなに?」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、いけばなの基本や始め方、必要な道具についてお伝えします。
毎日の生活にいけばなを取り入れてみたいという人は、ぜひ参考にしてください。
・いけばなに興味はあるが、何から始めたらいいかわからない人
・いけばなの基本的な情報を知りたい人
・いけばなを生活に取り入れたい人
目次
いけばなとは

いけばなは日本の文化を代表するものです。
室町時代、京都六角堂の僧侶であった池坊専慶が、座敷に飾った花が評判を呼び、それをきっかけにいけばなは武家社会や貴族社会へと広まっていったといわれています。
それまで仏前や神前に供えられていた花が、人々の生活空間にも飾られるようになったことで、日本独自の文化として発展していったのです。
室町時代は茶道や能など、さまざまな日本文化が生まれた時代でもあります。
現代のいけばなは生活空間に適応した表現がなされたり、海外からも大きな注目を集めており、時代や社会の変化に適応しながら発展を続けています。
いけばなを覚えるとどんなメリットがあるか
いけばなを覚えると、心が安定したり四季を感じられたりするというメリットがあります。
自然の美しさに触れることで日常の忙しさから解放され、心身の疲れやストレスを緩和します。
自然の彩りは癒しと活力を与えてくれ、花の香りによってリラックス効果が感じられます。
いけばなはストレスを感じやすい方におすすめの趣味といえます。
春には桜や梅、夏にはひまわり、秋には紅葉、冬には椿といった季節ごとの花材を用いることで、部屋の中でも季節を感じられます。
いけばなは四季の移ろいを通じて、忙しい日常生活の中で失われがちな心の余裕を取り戻してくれます。
いけばなとフラワーアレンジメントの違いは?
いけばなとフラワーアレンジメントはどちらも花を使いますが、美しさの表現方法や花の捉え方が異なります。
いけばなは日本の伝統的な文化です。
少ない花材でもはじめられ、花そのものが持つ自然な姿や生命力を表現します。また、余白や空間も美しさとして捉え、花材の位置や向き、組み合わせに意味を込め、季節感や自然との調和を表現します。
つぼみから開花、そして枯れていくまで、花の生涯全体を通してその美しさを楽しむことができるのも、いけばなの特徴です。
一方フラワーアレンジメントは、西洋から発展しました。
多くの花を使い、空間を花で埋めるようにして、その瞬間最も美しい花の姿を豪華に表現するスタイルです。
見た目の華やかさを重視し、プレゼントとして贈られることも多いです。
初心者でもいけばなを気軽に始められる理由

自宅で手軽にできる
いけばなは初心者でも気軽に始められます。
和装でお稽古に通ったり、本格的な器を用意する堅いイメージがありますが、毎日の暮らしの中に気軽に取り入れられます。
花材をわざわざ買わなくても庭の花を切って、玄関やリビング、ダイニングなどお家の好きな場所に飾り季節を楽しむのもいいでしょう。
器は家にあるグラスやマグカップ、ペットボトル、牛乳パックに折り紙を貼り付けたものなど、水の入る器であればなんでも構いません。
また花や草木を固定するのに、ビー玉やスポンジを剣山の代わりにもできます。
いけばな用の道具は100円ショップでも揃えられます。
花材を切るはさみや花器、剣山も買えますし、花用の栄養剤や水切り用のボウルなどもありますよ。
まずはお試しでいけばなを始めてみたいという方は、安く揃えられて気軽に使えるので100円ショップを覗いてみるのがおすすめです。
特別なセンスはいらない
いけばなを始めるのに特別なセンスは必要ありません!
いけばなには、基本となる型や構成があり、それらはいわゆる設計図のようなものです。この設計図に沿って、花材を組み合わせるように生けていくことで、誰でも美しい花を生けることができます。
最近ではいけばなの教室やオンライン講座も豊富にあり、用意されているカリキュラムに沿って教えられた通りに花を生けていけば、誰でも美しく花を生けることができます。
教室やワークショップが充実している
いけばなの作法を学びたい場合には教室に通うのがおすすめです。現在はいけばなの教室やワークショップが充実しています。
多くのいけばな教室では、基本から学べたり、資格取得を目指す人のお稽古があったりと、レベルに合わせたコースやカリキュラムが用意されています。
体験レッスン付きの教室もあり、初めての人向けのプログラムになっていることが多いので、初心者の方も安心して受講できます。
初心者におすすめのいけばなに必要な道具と材料

いけばな初心者におすすめの必要な道具と材料についてご紹介します。
花器
1つ目は花器です。
いけばなの花器は陶器の花瓶やガラスの器などたくさん種類がありますが、最初はシンプルなものを選びましょう。
形にデザイン性があると、それを活かす技術が必要になります。
色であれば白や黒、素材はガラス製を選ぶとシンプルでいいでしょう。
初心者さんにおすすめなのが水盤型の花器。口が広く底が浅い皿状の花器で剣山を使って生けます。
筒型の花器もおすすめです。筒型は丈が長く口の狭い花器で、枝を留めるタイプの花器です。
ハサミやその他の道具
2つ目はいけばな用のハサミや剣山などの道具です。
●花ばさみ…厚みのある枝や茎も簡単に切断でき、切れ味が鋭いのが特徴。使用後は必ず刃をきれいに拭き取り、さびないように手入れをしましょう。
●花留め(剣山やオアシス)…花を花器に固定するための道具。剣山は針がたくさんついており、花の茎を挿して固定します。オアシスは吸水性のスポンジで、特に吸水が必要な花材に適しています。花留めを使用することで、花の位置が安定し美しい構図を保てます。
<あれば便利な道具>
●花バケツ…花材を一旦保管できます。手持ちの花瓶や深めのバケツでも代用可能。
●ボウル…水を張り、枝や茎の先を水中に入れて花ばさみを使ってカットします。
●水差し…花器に水を入れるときに使う。やかんでも代用できます。
●剣山おこし…剣山を持ち上げるための道具。剣山の針に触れることなく、安全かつ簡単に剣山を使用できます。
●エプロンや割烹着…作業中の衣服を水や汚れから守ります。
花材
3つ目は花材です。
初心者にとって、使いやすく手に入りやすい花材を選ぶことは重要です。
比較的生けやすい花材をご紹介します。
●菊(きく)…日本の伝統的な花で、丈夫で長持ちします。季節を問わず手に入れることができ、色や形のバリエーションが豊富です。
●カーネーション…豊富な色合いと形状を持ち、香りも良い花です。花持ちが良く、長期間楽しめます。
●バラ…美しい形と香りが特徴の花。シンプルなアレンジでも豪華さを演出できます。花材が少なくなる冬でも手軽に手に入ります。
●ガーベラ…華やかな色合いと花びらの広がりは人目をひきます。単体でも作品のメインとなりますが、背の高い花材と合わせて生ければ作品全体の印象をグッと引き締めてくれます。向いてほしい方向をしっかり向いてくれる優秀な花です。
●ひまわり…親しみ深く、そこにあるだけで夏らしさを演出してくれます。季節を楽しむことはいけばなにおける大切な要素の一つです。葉が柔らかいので、手でプチプチと簡単に摘めて調整できます。
いけばなを始めるにはどうすればいいか

いけばなを始めたいけど、どうすればいいかわからない方は教室に通うのがおすすめです。
いけばな教室では基本的な生け方を学ぶことができます。
まずは体験レッスンから初めてみるのがおすすめ。お手頃な価格で初めての人向けのプログラムになっているので、初心者でも気軽に参加できます。
仕事帰りに立ち寄れる場所など、自分のライフスタイルに合わせて無理なく通える教室を探しましょう。
近くに教室がない方や忙しく時間がない方は、オンラインのいけばな教室もおすすめです。
花ばさみや花器、花材などの他に、スマートフォンやタブレット、パソコンなどの端末とオンライン環境さえあれば自宅で気軽にいけばな教室を受講できます。
まとめ
今回はいけばなの基本や始め方、必要な道具について紹介しました。
いけばなは日本の伝統的な文化であり、心が落ち着くなどのメリットもあります。
初心者でも気軽に始められ、体験教室やオンライン講座などもあるので、興味のある方はチェックしてみてください。
忙しい日常に彩りを加えて、心豊かに過ごしましょう。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
この記事を書いた人
なついろ
フリーランスライター
青森県在住、2児の母。
何歳からでも学び直しはできると一念発起し、30代からライター活動を開始。
SEO記事の執筆や取材記事を中心に活動。生まれ育った青森県の地方創生に関連した活動に力を入れている。
得意ジャンルは地方創生・子育て・暮らしなど。
もっと学びたい方へ|割引クーポンプレゼント!
感想をお寄せくださった方全員に、N-Academy「はじめてのいけばな講座」の10%割引クーポンプレゼント実施中。
クーポン対象講座

編集者情報
 |
株式会社デジタル・ナレッジ サービス推進事業部 事業部長 野原 成幸 |
| わからないことはインターネットで検索していた時代から、AIに質問することでさらにスピーディーに解決できる時代になりました。多くの場合、解決して終わりだと思いますが、「これについてもっと知りたいな」「学んでみたいな」ということも少なからずあるのではないでしょうか。 Pre.STUDYでは、何かを学びたいと思って検索する人にとっての学びの予習(prestudy)になり、明日誰かに話したくなる情報を発信しています。それと同時に、なんとなく湧いた疑問を検索した先で、ふと芽生えた知的好奇心をくすぐり、学びのきっかけになるメディアを目指しています。 | |